















WSDとは?
青山学院大学ワークショップデザイナー(WSD)育成プログラムでは、
ワークショップが必要とされる社会的背景と学習観の変容、
コミュニケーション論などを学び、実際にワークショップを体験します。
さらに、ワークショップを企画・実践し、振り返ることを通して、
理論と実践をつなげながら学ぶことができます。


ワークショップデザイナーとは、「コミュニケーションの場づくりの専門家」です。
「コミュニケーション」とは、身近なコミュニケーションから
地域・社会のコミュニティなど広い範囲を考えています。
「場づくり」とはコミュニケーションが促進される
コンテンツ(内容)、スペース(空間)、チャンス(出会い)をデザインしていくことだと考えています。
「専門家」とは、異分野や異文化の垣根を越境したり、横断したりして、つながりをつくり、
新しい価値観を生み出すことができる専門性を持った人を意味しています。
では、ワークショップデザイナーは、どんなことをする人なのでしょう。
それは、これからの社会を少しでも良いものにしていくため、さまざまな「協働」の結び目になる人です。
私たちが考えている「より良い社会」とは、
グローバル化、情報化、高齢化、などに対応できる、持続可能な多元的共生社会です。
時代の変化とともに複雑化していく社会の中で、「コミュケーションの場」の必要性は高まっていきます。
今まさに、人と人、コミュニティとコミュニティの「結び目」の機能を果たしていける、
「コミュニケーションの場づくりの専門家」としてのワークショップデザイナーが必要とされているのです。
ワークショップデザイナーは偉い先生でもなんでも解決出来るスーパースターでもありません。
しかし、ワークショップという手法を潤滑油として、場を通して考えていくことの可能性と限界を模索できます。
つまり、共に一歩を踏み出すことを試そうとするのがワークショップデザイナーなのです。


履修証明制度とは、学校教育法第105条及び学校教育法施行規則第164条の規定に基づき、大学が教育や研究に加えてより積極的な社会貢献として、主として社会人向けに体系的な学習プログラムを開設し、その修了者に対して、法に基づく履修証明書を交付するものです。
本プログラムも、特色ある教育プログラムを作り、社会人等に多様な分野の学習機会を提供することを目指したものです。120時間の講座を修了すると、青山学院大学から学校教育法にもとづく履修証明書が発行されます。
青山学院大学履修証明プログラム修了ワークショップデザイナー
Aoyama Gakuin Univ. Program Certified Workshop Designer
※ワークショップデザイナー(Workshop Designer)のみの記載でも問題ありません。
※取得した履修証明は履歴書や名刺に記載できます。
※履修証明書記入欄のある履歴書も発売されています。
※履修証明制度については文部科学省のホームページをご覧ください。

ワークショップデザイナーは「コミュニケーションの場づくりの専門家」を意味している。ここでいう「コミュニケーションの場」は、自分の当たり前と異なる当たり前を持っている人とのコミュニケーションの場のことである。つまり、ワークショップデザイナーは、異質な当たり前を結んでいく役割を持っている。しかし、異質な当たり前を結んでいくことは、とても難しい。それぞれの人が持っている自分の当たり前は無意識なものが多く、異質なものと出会ったとき、「遠慮という排他」「気遣いという同化」など、自らの当たり前を変えることなく異質な他者を変えていこうという意識のぶつかり合いが起きていく。
私たちはワークショップでそれらの課題をすべて解決できるというような、過大な期待は持っていない。それは、一人のカリスマ的なリーダーが一つの万能薬のような方法で何もかも解決してくれるという他力本願的な考えを持っていないということである。私たちは万能薬としてのワークショップは期待していないが、ワークショップの可能性を捨てているわけではない。なぜなら、「現場」という状況には、その「現場」ならではの課題や、課題そのものの場所(Local)や期間(Temporary)が限定的だからである。
そのLocalでTemporaryな課題には、それにフィットしたワークショップをデザインする必要があり、フィットしたワークショップは、課題の解決に効く場面がある。それがワークショップの可能性なのである。
これからの社会では、社会や産業の構造が変化し、経済的自立を果たすために複数の組織やコミュニティに参加していくことが求められていく。そこでは、地縁、血縁、組織縁だけではなく、志縁、偶発的な縁などいろいろな種類や規模の多様な価値観を持ったコミュニティが共存することになる。そして、人々が互いを認め合ったり、支えあったりする関係が重要になっていき、解決すべき問題ごとに複数のコミュニティや個人が協力してユニットをつくっていくようになる。それを協働と呼び、協働が習慣のようになっていくことが求められる。この協働の習慣化のために、ワークショップデザイナーには、さまざまな共同体の内外でコミュニケーションの場を提供していくことが求められていく。
その一翼をぜひみなさんに担ってもらいたい。
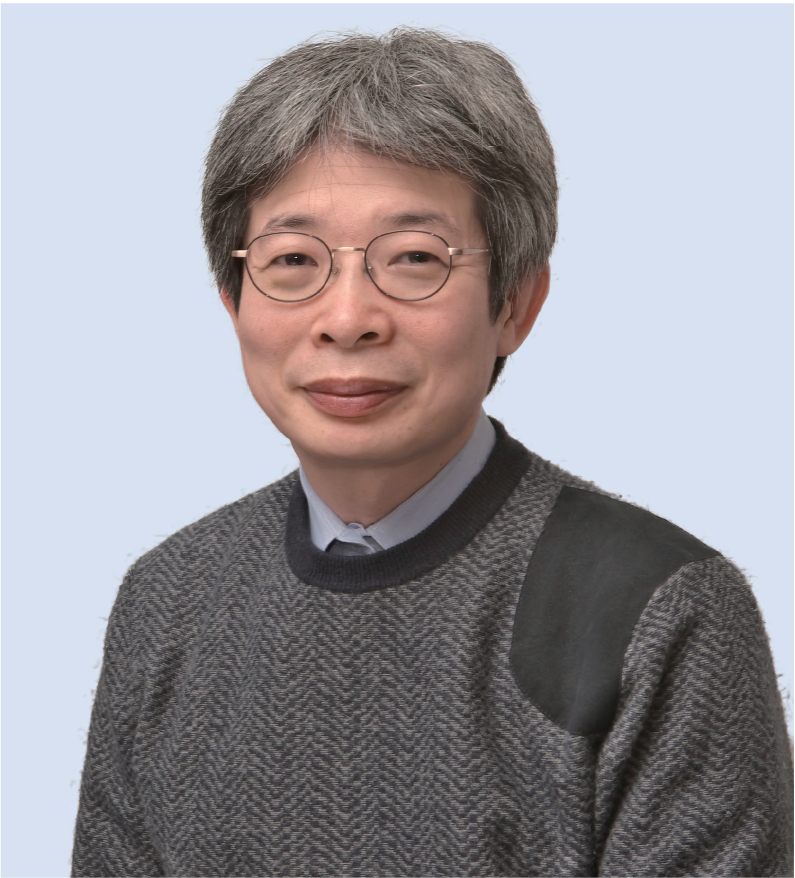
この「ワークショップデザイナー(WSD)育成プログラム」が、これほどの発展を見せるとは、正直、思ってもいなかった。
今でこそ、多くの方が口コミで内容を知ってから受講するが、初期には、「もう少しきちんと教えてください」という声をいただいたこともあった。ここで言う「きちんと」とは「体系的に」ということなのだと思う。
クライアントの立場の人々(企業の人事担当や行政の管理職)と、コーディネーターを目指す人々(アート系・教育系のNPOや、公共文化施設の職員)、ファシリテーターを目指す人々(アーティストや教員)が、渾然一体となって授業を受けることが、WSD育成プログラムの最大の特徴である。
体系的に「きちんと」教えようとするなら、これらのステークホルダーには別々のカリキュラムを授けた方が効率的だっただろう。しかし私たちは、その「効率」を求めなかった。
実際に、日本のワークショップの現場では、その是非はともかくとして、クライアント、コーディネーター、ファシリテーターが境界を曖昧にして仕事を進める。
一つの役割のためだけの知識では、ワークショップを運用できない。また、そうでなくても、お互いがお互いの立場を理解していた方が作業は円滑に進むし、相乗効果も生まれるだろう。
なによりワークショップとは、世界の混沌や不条理を効率よく整理するのではなく、解像度をあげて課題を鮮明に示すことにその利点がある。私たちを苦しめているものはなんなのか、私たちの悩みの実体はどこにあるのか、あるいは希望は?
簡単に言葉や形にならないものを、ワークショップは、時間をかけて共有していく。その共有のプロセスにこそワークショップの醍醐味があり価値がある。
本講座で目指されるワークショップデザイナーとは、そのような一筋縄ではいかない「世界」に対して、たじろがず、開き直らず、しっかりと向き合って、ワークショップをプログラムできる人々のことを指す。何より重要なのは、勇気と謙虚さである。その矛盾を受け入れることである。
文部科学省社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム事業を受託
青山学院大学・大阪大学の共同事業として「ワークショップデザイナー育成プログラム」開講
鳥取大学で開講
文部科学省社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム事業委託期間 終了
ワークショップデザイナー育成プログラム修了生 1000人突破
日本の人事部「HRアワード」プロフェッショナル教育・研修部門最優秀賞 受賞
グッドデザイン賞・グットデザインベスト100未来づくりデザイン賞 受賞
文部科学大臣認定「専門実践力教育プログラム(BP)」認定
ワークショップデザイナー育成プログラム修了生 2000人突破
オレンジコース、ブルーコース2コース制開始

