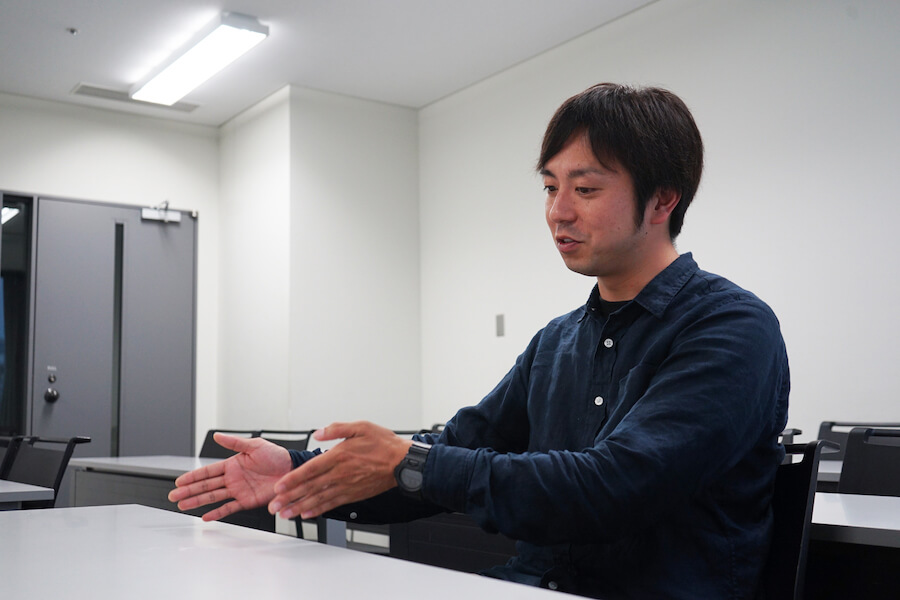田上豊Profile
1983年熊本県生まれ。桜美林大学文学部総合文化学科卒業。2006年、劇団「田上パル」を結成。方言を多用し、 疾風怒濤のテンポと、遊び心満載の演出は「体育会系演劇」とも評される。大学在学中にワークショップデザインを研究し、現在、 教育現場を中心に、創作型、体験型のワークショップを全国各地で実施している。演劇部の嘱託顧問や、総合高校での表現科目「演劇」の授業を受け持つなど、教育現場での経験も持つ。高校生、大学生とのクリエーション、リーディング、市民劇団への書き下ろしなど、劇団外での創作活動も展開。現在、富士見市民文化会館キラリふじみアソシエイトアーティスト、青年団演出部所属。
古くから、学校は先進的な知的生産の場でした。なぜなら、学校でしかできないことが多かったからです。例えば、ピアノの演奏や映像の鑑賞、パソコンの操作、外国語の習得などです。しかし現代では、学校は情報化や国際化に関わる知識や技能、研究的視点、地縁的な関係性などを学校外から学ぶ必要が出てきました。なぜなら、学校でしかできなかったことが、学校外でできる時代になったからです。そこで、今までのパッケージ化した教えを越境し、新しく柔軟な考え方を取り入れて行く必要があります。
学校が凝り固まったこれまでのやり方を見直さなければいけない局面にある中で、アーティストが学校教育に参入し、ワークショップ等の表現活動を行う事例が多く見られます。彼らはどのような思いを持ち、学校での活動を行っているのかをインタビューしました。
ワークショップデザイナー育成プログラムや学部の授業である「ワークショップデザイン/メディア・コミュニケーション」に講師として来てくださっている演出家の田上豊さんに、2018年に行われた田上パル第17回公演「Q学」のお話や、ワークショップについてお話を伺いました。