



ワークショップデザイナー®(WSD)とは、
「コミュニケーションの場づくりの専門家」です。
コミュニケーションを基盤とした参加体験型活動プログラム(ワークショップ)の、企画運営を専門として行うことができる人です。会社組織、医療、福祉、教育現場、地域コミュニティ、アートなどさまざまな、コミュニケーションを必要とする現場でその専門性が求められています。
ワークショップデザイナー育成プログラムは、
ワークショップデザイナーになることを目指す社会人向け履修証明プログラムです。
ワークショップの理論と実践を体系的に学ぶことができます。理論を学び、それを活かしながらワークショップを実施することで実践力をつけます。

 こんな人におすすめ!
こんな人におすすめ! 多様なバックグラウンドの大人がグループになり、ワークショップをつくるというひとつの目的に向かって学んでいきます。他者と学びを共有することで、視点を広げたり、自分の当たり前に気づいたり、協働的な学びから、ワークショップの本質を探ります。
オンライン・オフラインともに、自分の体験したことをていねいに省察することから学ぶスタイルを基本としています。素直に感じたこと、他者の視点から見えたこと、分析的に捉えることなど、学びの段階、内容に合った多様な手法での省察から、自分なりの学びを獲得できます。
「ワークショップの体験・企画・実践・省察」を2回繰り返すことで、経験を通じた「納得解」を導きだします。学んだ知識を経験と結びつけ、1回目の経験を2回目に活かしていくことで多角的に知識を捉え、実際に使ってみることを通して学びの深まりを体感できます。

自身のライフスタイルに合わせて、コースを選択できます。

※通学対面授業・リアルタイム型オンライン授業は土日となります。

※リアルタイム型オンライン授業は平日夜がメインとなります。
(一部、土日もあります)

ワークショップの背景理論について、学習科学・社会学などの視点から講義とワークを通して学んでいきます。
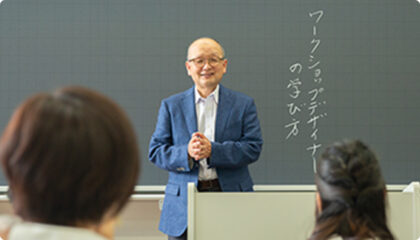

グループでワークショップの企画、実践、省察までを体系的に学びます。プログラムの中に、コミュニケーションを促進するための仕掛けを、どのように組み込むかなどを意識して取り組みます。


企画・実践・省察の流れをもう一度繰り返すことで、理論と実践を結びつけ、さらに学びを深めます。ワークショップ実践科目Ⅱでは、特にファシリテーションのスキルアップを目指します。


カリキュラム全体の振り返りとして、2回の実践での学びをワークショップを通して概念化していきます。


| 主催 | 青山学院大学社会情報学部 |
|---|---|
| 時間 | 120時間 |
| 期間 | 約3ヶ月間 |
| 開催時期 | 年間2期開講 ※詳細なスケジュールは年度毎に異なります。 |
| コース紹介 | ▶︎オレンジコース ▶︎ブルーコース |
| 人数 | 1期あたり120名程度(オレンジコース80名・ブルーコース 40名) |
| 応募資格 | 高校卒業以上、及びそれと同等の学力があるとみなされた方 |
| 取得証明 | 青山学院大学学校教育法履修証明プログラム修了ワークショップデザイナー |
| 受験料 | 5,000円(非課税) |
| プログラム受講料 | 278,000円(非課税) |
オレンジコース・ブルーコースともに
278,000円(非課税)
最大80%(※受講料278,000円(非課税)に対して)
222,400円 給付
※当該訓練講座の詳細は、明示書をご参照ください。
※専門実践教育訓練のご質問については、最寄りのハローワークにお問い合わせください。
また、詳細な制度説明とパンフレットについてはハローワークインターネットサービスのホームページをご覧ください。
※3の条件は2024年10月以降に開講の講座に適用されるため、本プログラムの場合は、2025年度受講生から該当します。
※教育訓練給付金については、厚生労働省のホームページをご覧ください。
企業人事・研修講師、公務員、アーティスト、学校教員、医者、看護師、役者など、様々なフィールドや専門性を持った人が集まるからこそ、できる学びあります。
年齢層も20代~60代まで幅広く、様々な経験値の人がフラットな関係性の中で学んでいます。

ブルーコースはすべてがオンラインだったということもあり、起こる出来事はすべて「画面越し」でした。そういう状況だったからこそ、その時々で、目に見えているものや相手が発している言葉の向こう側に隠れている真意のようなものの存在を感じ取ることの重要性を学びました。<br>修了後は、ワークショップに限らず仕事や日常生活でも、まず目の前で起こっていることをありのままに受け止めてしっかり傾聴しさらにその奥を感じようとすることで、相手への理解が深まり、自分の思考にも幅が生まれたように思います。

介護士・ケアマネジャー・看護師・管理部門など様々な立場や専門職がいる介護・福祉職で、多様な意見をまとめていくことに学びが活きていると感じています。一人ひとりの当たり前は違うという前提があり、その違いを意識しながら新しいものを創っていく、みんなで合意形成をしていくプロセスを体系的に学べ、身をもって体験(実践)できるので、その経験がお客様とのディスカッションの場や、コンサルティング、人との人間関係など様々な場面に活かせているなと感じています。

プログラムをデザインする上で、段階的に難易度を上げていくことやモデリングの重要性など、細かな参加保証する仕掛けや足場かけを意識することの重要性を、実践しながら学びました。
受講後は、かなり時間をかけてデザインをするようになり、繋がりのあるワークショップを考えるようになりました。またワークの難易度も参加者によって異なるということを、WSDの授業を通して身に染みて感じたので、なるべく自分1人で考えるのではなく、周りから意見をもらうことで、沢山の気づきを得られています。

青山学院大学社会情報学部教授。Ph.D.(Ed)
ワークショップに代表される協働的な学習を実践的に研究している。特に学校教育で展開されているアート系ワークショップの調査研究をしている。
専門は、学習コミュニティデザイン論、学習環境デザイン論、教育工学。 リアルコミュニケーションツール「Vitamin Happyビタハピ」や「逆転時間ワークショップ」などでグッドデザイン賞やキッズデザイン賞を受賞。著書には「ワークショップと学び」(編)[全3巻](東京大学出版会)など多数。

青山学院大学社会情報学部プロジェクト准教授/ワークショップデザイナー育成プログラム 事務局長
NPO学習環境デザイン工房のスタッフとして、学校やミュージアムにてワークショップの企画・運営を多数実施。2008年より、ワークショップデザイナー育成プログラムの立ち上げに携わり、講師、カリキュラム設計、オンデマンド教材制作を行っているかたわら、ワークショップ、インストラクショナルデザインの研究に携わる。その他リアルコミュニケーションツールの開発にも関わり、グッドデザイン賞やキッズデザイン賞など多数受賞。著書には、「ワークショップと学び」2,3巻(共著)など。

慶應義塾大学工学管理工学科卒業、同大学院管理工学専攻修士課程修了後、米国ワシントン大学大学院心理学専攻に入学、1970年同博士課程修了(Ph. D.)1971年4月より東京理科大学理工学部助教授、1981年4月より東京大学教育学部助教授、同教授を経て2000年3月に東京大学を定年退官し、東京大学名誉教授となる。同年4月より青山学院大学文学部教育学科教授、2008年4月より、同社会情報学部教授、2013年3月に退職し、青山学院大学名誉教授となる。2012年4月より公益社団法人信濃教育会教育研究所所長、2015年4月より田園調布学園大学大学院人間学研究科子ども人間学専攻教授、2021年3月退職。
主著:『幼児教育へのいざない』東京大学出版会2001年、『共感—育ち合う保育のなかで』(編著)ミネルヴァ書房2007年、『ワークショップと学び』(編著)[全3巻]東京大学出版会2012年、『子どもを「人間としてみる」ということ』(編著)ミネルヴァ書房2013年、『「子どもがケアする世界」をケアする』(編著)ミネルヴァ書房2017年、『ビデオによるリフレクション入門』(編著)東京大学出版会2018年、など。

劇作家・演出家・青年団主宰。
こまばアゴラ劇場支配人。1962年東京生まれ。国際基督教大学教養学部卒業。1995年『東京ノート』で第39回岸田國士戯曲賞受賞。1998年『月の岬』で第5回読売演劇大賞優秀演出家賞、最優秀作品賞受賞。2002年『上野動物園再々々襲撃』(脚本・構成・演出)で第9回読売演劇大賞優秀作品賞受賞。2002年『芸術立国論』(集英社新書)で、AICT評論家賞受賞。2003年『その河をこえて、五月』(2002年日韓国民交流記念事業)で、第2回朝日舞台芸術賞グランプリ受賞。2006年モンブラン国際文化賞受賞。2011年フランス国文化省よりレジオンドヌール勲章シュヴァリエ受勲。
東京藝術大学社会連携センター特任教授、大阪大学客員教授、四国学院大学学長特別補佐、(公財)舞台芸術財団演劇人会議理事長、埼玉県富士見市民文化会館キラリ☆ふじみマネージャー、BeSeTo演劇祭日本委員会委員長、日本劇作家協会副会長、日本演劇学会理事、(財)地域創造理事、東京芸術文化評議会評議員、文部科学省コミュニケーション教育推進会議委員(座長)。

青山学院大学社会情報学部プロジェクト教授/G office 代表
1969年東京都生まれ。学生時代より俳優活動を始め、1995年に初舞台、2003年に初演出。HB Studio(New York)で演技技術を、RADA(London)で シェイクスピア演技を学ぶ。自身の活動のほか、子どもから大人までの演技や表現の指導にも携わる。また演劇活動と並行して、1997年より大学や企業研修の講師として活動を始める。 現在、官公庁や大手企業を中心に若手から管理職まで幅広い対象者に向けて、主にワークショップ型の研修を提供している。
他多数
他多数
最終学歴が高校卒業以上(同等以上の学力があると認められる方を含む)です。出願の際、最終学歴の卒業証明 書または卒業証書のコピーが必要になります。
あります。提出していただく書類審査(願書、小論文)とオンライン面接にて、総合的に判断します。
受験料は5,000円(非課税)です。詳しくは出願申請をご覧ください。
振込での一括払いになります。また、振込明細書をもって領収書と代えさせていただきます。振込後の受講料の返還はいかなる場合でもできませんのでご注意ください。
ありません。ただし、通学対面授業の交通費とオンライン授業の通信費は自己負担となります。
お住まいの地域(所轄)のハローワークにお問い合わせください。
オンライン授業があるため必要です。リアルタイム型オンライン授業はzoom を使用します。zoom に接続できる インターネット環境があり、ノートパソコン・デスクトップパソコンであれば受講できます。スマートフォン、タ ブレットでの受講はご遠慮ください。
お仕事やご家庭の都合など、やむをえない理由で欠席される場合には、補講を受けていただき、出席を代替するこ とが可能です。
課題は、教材ごとに出題されます。600 〜1,200文字のレポートが中心になります。